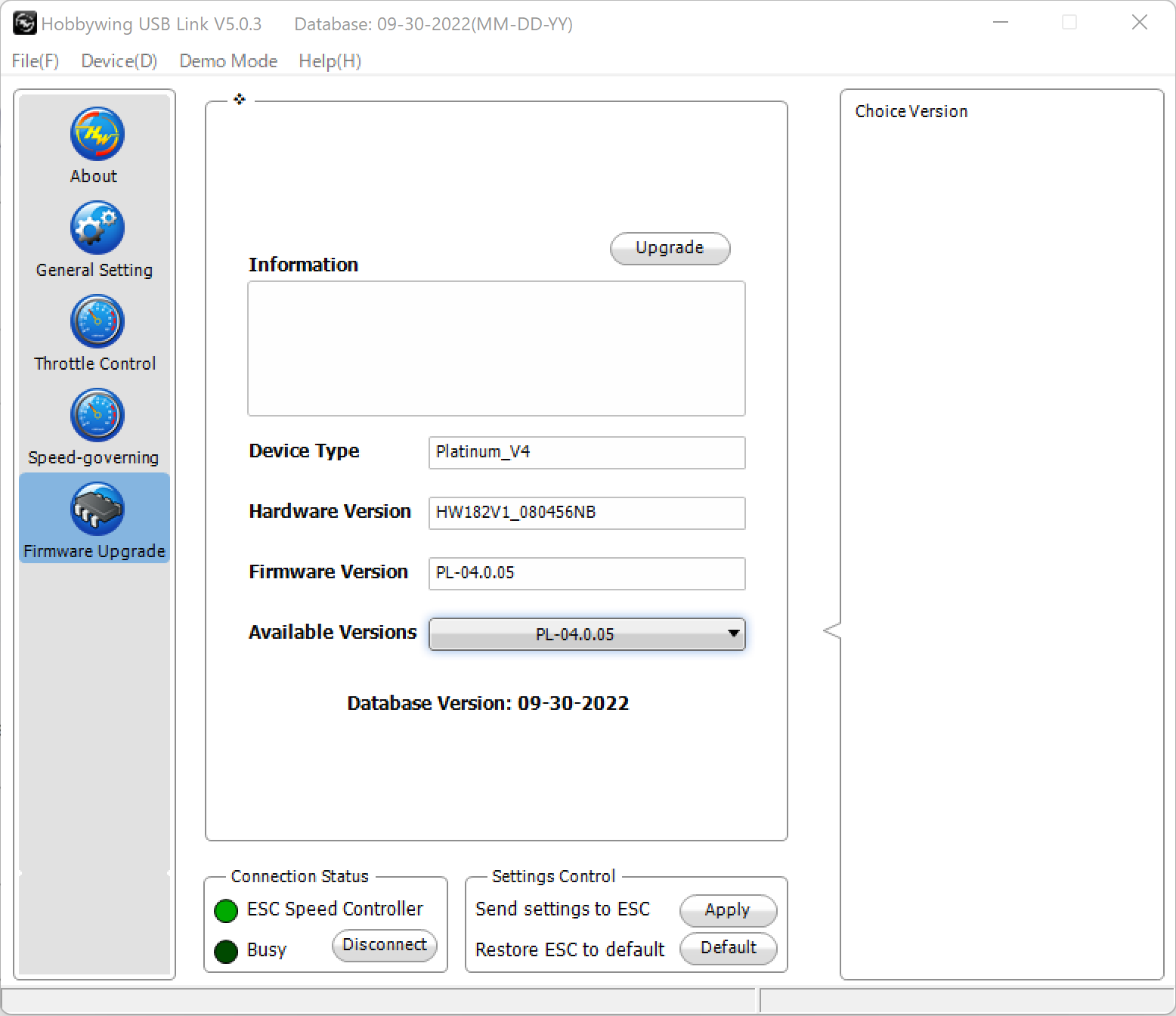土曜日。娘の運動会後に待望のお時間。(もちろん運動会も待望だったが、このブログ的にはと補足しておく)
先週のドタバタは何処へやら、すんなり飛んでくれた! 機体の重さとか全く気にならんほどの浮き。それでいてフワフワせずにビシッと浮いててくれる。T-Rex の同サイズはフワフワしてて嫌な感じだったけど、全然違う!HIROBOのLeptonExをさらによくした感じ!(言い過ぎでは無いと思う)
こいつは良いヘリですわ( ´∀`)
この日はバッテリ2本、翌日は少し風強めだったけどそれほど気にならずバッテリ3本調子よく飛ばせた。
ただし、、、6年のブランクに加え、スタビ無しで飛んでいる事の違和感が脳から拭い切れないからなのか、飛ばすのが怖いw
土曜日はケツ向けてのホバリング止まり。日曜はバッテリ3本かけて、おっかなびっくり側面向けてのホバリングまで。これはしばらくリハビリが必要そうだ( ;∀;)
シミュレータでは何も問題なく飛ばせたんだけど、本物飛ばすのは違いますなぁ。
初めての飛行機着陸で足震えて(本当にガクガク震えた)クラブのメンバに大笑いされたのを思い出したよ、、。
いくつか課題は出たけど、次の更新のネタにとっておく。今週は無事飛ばせましたって事で。
本日はここまで。